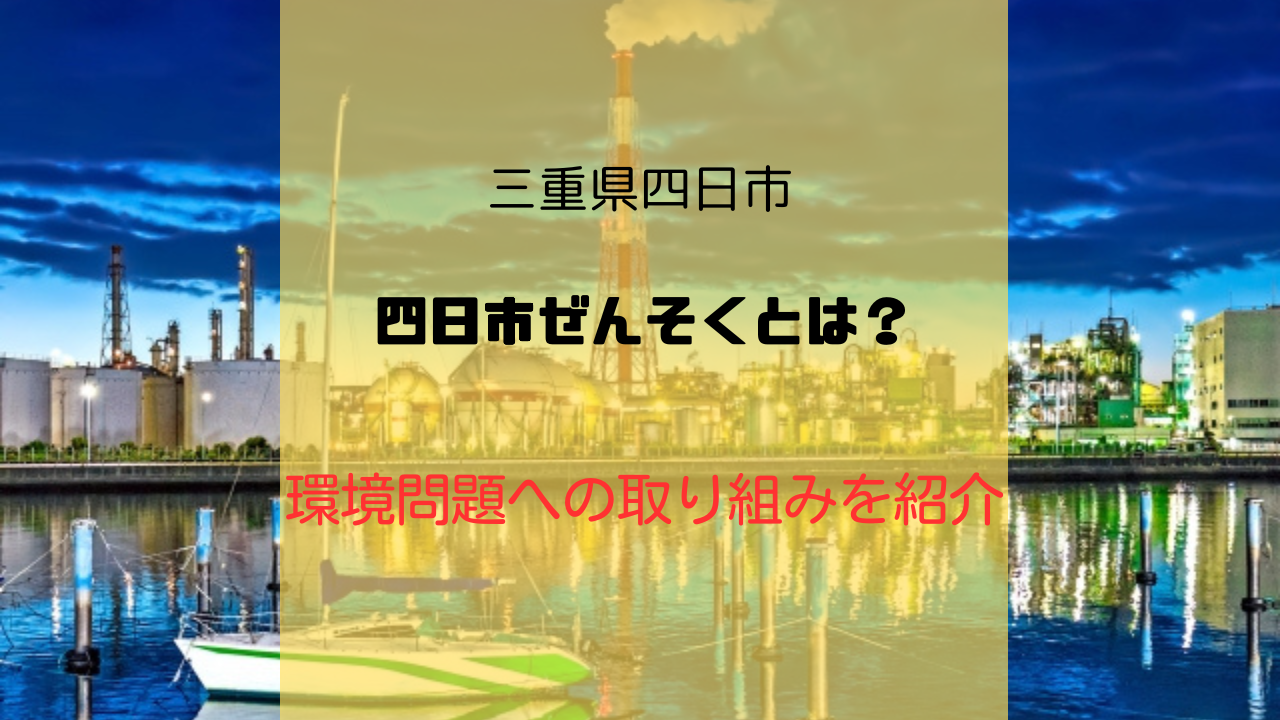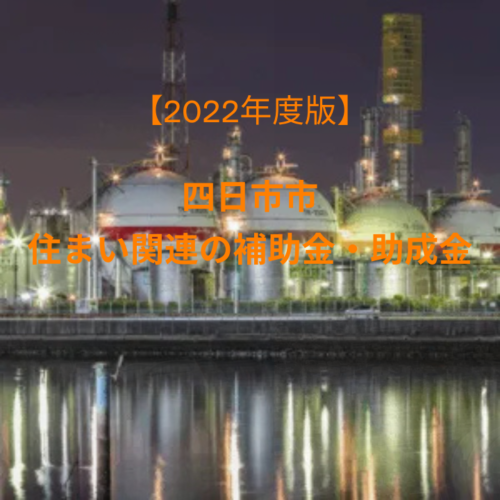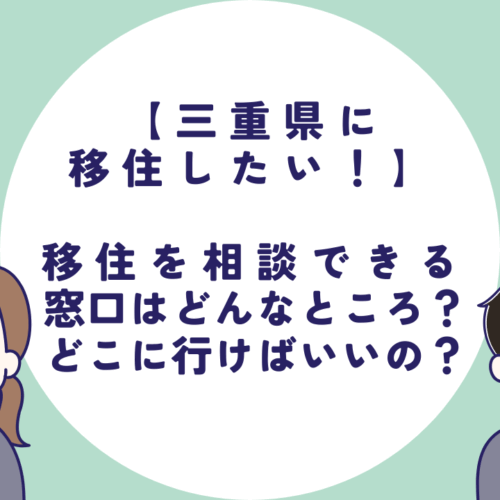四日市市といえば「四日市ぜんそく」という公害を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。四日市ぜんそくとは日本の歴史の中でも非常に大きな公害の1つであり、多くの被害者を出してしまいました。四日市市は全国でも有数の工業地帯であり、市民の生活のためには工場が欠かせません。
だからこそ、四日市市は公害を再発させないために様々な取り組みを行っています。本記事では、四日市市の公害に関する歴史や対策に向けた取り組みについて徹底解説します。
四日市市の公害「四日市ぜんそく」とは?

四日市市の「公害」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのが「四日市ぜんそく」です。1960年代に日本各地で問題となった四大公害病の1つであり、大気汚染によって多くの市民が健康被害を受けた深刻な社会問題です。そのため、四日市市は公害問題の象徴ともいえる地域であり、現在に至るまで「公害からの復興」というテーマと向き合い続けています。
四日市公害の中心となったのは、石油化学工場やコンビナート群から排出される有害物質でした。特に、二酸化硫黄(SO₂)が大量に大気中へ放出されたことで、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器疾患を訴える市民が急増しました。当時は高度経済成長の真っ只中であり、産業発展が最優先されたことで、環境対策が後手に回ってしまったのです。
特に深刻だったのは、四日市市の臨海部、現在の四日市コンビナート周辺に住んでいた住民です。この地域では、工場の煙突から出る煙やガスが風向きによって住宅地に流れ込み、慢性的な大気汚染が発生していました。子どもから高齢者まで多くの市民がぜんそく症状を訴え、日常生活にも深刻な影響を及ぼしました。
この公害問題は、1967年に「四日市ぜんそく」の被害者が企業を相手に損害賠償請求訴訟を起こしたことでも注目されました。そして1972年、被害者側が勝訴したことで、四日市市における公害対策の転機となり、その後の日本の環境政策にも大きな影響を与えました。
四日市ぜんそくは四日市市や三重県だけではなく、日本全国に影響を与えた非常に大きな問題だったといえるでしょう。
四日市市の公害対策
四日市市は現在では公害の影響を心配することなく、安心して暮らせる街になっています。そのような街に変化したのは、四日市市が一丸となって公害対策に取り組んだからです。ここでは、四日市市の公害対策の代表的な取り組みについて紹介します。
公害防止協定の締結
1960年代後半、四日市市は公害の原因とされていた企業との間で「公害防止協定」を締結しました。これは企業側に対して大気汚染物質や排水の排出量を規制するもので、国内初の試みとして注目を集めました。
協定の内容には、二酸化硫黄の排出量の削減や、監視体制の強化などが含まれており、市と企業が協力して公害問題の解決に向けて動き出したことを象徴する重要なステップとなりました。
モニタリング体制の強化
公害対策として不可欠だったのが、環境データの可視化です。四日市市では1970年代以降、大気や水質の常時監視体制を整え、コンビナート周辺に大気観測局を複数設置しました。
これにより、二酸化硫黄や窒素酸化物、粉じんなどの濃度をリアルタイムで把握し、異常値が出た際にはすぐに企業に対処を求める体制が構築されました。市民にも定期的にデータが公開され、透明性のある取り組みが評価されています。
クリーンな工場への転換促進
四日市市は、企業がクリーン技術を導入し、より環境負荷の少ない生産体制に移行することを促しました。1970年代からは大規模な設備投資を通じて、脱硫装置や排ガス処理装置などが次々に導入され、工場排出物の浄化が進みました。
行政側も補助金制度や技術支援などを通じて、企業の環境配慮型経営への移行を後押ししました。その結果、四日市の空気質や水質は大幅に改善され、1970年代後半には「公害のまち」から「環境改善都市」へと評価が変わるきっかけとなりました。
市民参加型の環境保全活動
公害対策の成功には、市民の協力と理解も不可欠でした。四日市市では、小中学校での環境教育をはじめ、市民参加型の清掃活動や植樹活動なども積極的に展開されています。
また、「四日市市環境フェア」などのイベントでは、公害の歴史を学ぶパネル展示やエコ活動の紹介が行われており、次世代への啓発にも力を入れています。
医療と生活支援の強化
公害によって健康を害した市民に対する医療支援も、四日市市の対策の一環として重視されてきました。国の「公害健康被害補償制度」に基づき、医療費の自己負担軽減や定期健診の実施が行われており、症状を持つ方々が安心して暮らせる体制が整備されています。
生活支援制度も並行して整備され、住宅環境の改善や福祉サービスの拡充などが進められてきました。
現在の四日市市の環境と評価
かつて「公害の象徴」とも呼ばれた四日市市ですが、長年にわたる公害対策と地域全体の努力により、現在ではクリーンな都市として再評価されつつあります。以下では、現代の四日市市がどのように環境を改善し、どのような評価を受けているのかを詳しく解説します。
大気や水質の大幅な改善
かつては深刻な大気汚染に悩まされていた四日市市ですが、現在では環境基準を大きく下回る良好な空気環境が維持されています。環境省や市のモニタリング結果によると、二酸化硫黄や浮遊粒子状物質(SPM)などの有害物質は、年々減少傾向にあり、全国平均と同等あるいはそれ以下の数値を保っています。
また、水質も改善され、四日市港周辺の海域ではアサリや海苔の養殖が行われるなど、かつての「死の海」とは一転し、豊かな生態系が戻りつつあります。地域住民や観光客が海沿いでレジャーを楽しむ姿も多く見られており、環境が問題視されていた昔の姿はないといえるでしょう。
環境共生都市としての取り組み
四日市市は現在、「環境と産業の共生都市」を目指して多方面から環境政策を展開しています。産業都市としての機能は維持しつつ、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入、ゼロエミッションへの取り組みなどを推進しています。企業にも環境配慮型経営を促し、次世代に持続可能なまちづくりを進めているのも特徴です。
また、市独自の「環境基本計画」では、脱炭素社会の実現を見据えた目標が掲げられており、これには市民・事業者・行政が一体となって取り組む姿勢が明記されています。単なる「対策」ではなく、「共生」や「再生」に軸足を移している点が、現代の四日市の特徴といえるでしょう。
国内外からの高い評価
環境問題に真剣に向き合い、再生を果たした四日市市は、今では全国の自治体や海外の行政関係者からも注目を集めています。例えば、環境学習のフィールドワーク地として、四日市市を訪れる学生・研究者が増加しており、地域ぐるみで「公害から学ぶ」活動が活発化しています。
また、国際会議や視察の受け入れも行っており、「公害から立ち直ったまち」として、持続可能な都市づくりのモデルケースと評価されるようになりました。四日市の成功事例は、日本国内の他地域や発展途上国においても参考とされることが多く、まさに「負の遺産を未来の力に変えた都市」といえるでしょう。
四日市市の環境を守るために私たちができること

かつて深刻な公害を経験した四日市市は、市民・企業・行政が一体となって環境改善に取り組んできた結果、現在では持続可能なまちづくりのモデル都市として注目されています。こうした取り組みを未来につなげていくためには、私たち一人ひとりが日々の生活の中で環境への配慮を意識することが不可欠です。
ここでは、四日市市の環境を守るために私たちができることをいくつか紹介します。
ごみの分別とリサイクルの徹底
家庭ごみの適切な分別とリサイクルは、誰でも今すぐに始められる環境保全活動です。四日市市では細かな分別ルールが定められており、資源ごみ・可燃ごみ・不燃ごみなどを正しく分けることで、焼却時のCO₂排出量を減らすと同時に、再資源化による資源の有効利用が進みます。
また、リサイクルステーションの活用や、使い捨て製品の削減にも積極的に取り組むことで、環境への負担を大きく軽減できます。
省エネ・節電の習慣を身につける
家庭や職場でのエネルギー使用を見直すことも、温室効果ガスの削減に繋がる重要な取り組みです。不要な照明をこまめに消す、エアコンの設定温度を適正に保つ、省エネ家電への買い替えを検討するなど、日々の小さな行動が積み重なれば、大きな環境負荷の軽減につながります。
また、太陽光発電の導入や再生可能エネルギーの選択も、将来的に環境にやさしい暮らしを実現するうえで有効です。
地元の環境保全活動に参加する
四日市市では、地域の清掃活動や緑化活動、環境イベントなど、さまざまな市民参加型の取り組みが行われています。自治会やNPO団体が主催する活動に参加することで、地域とのつながりを深めながら、環境への意識を高めることができます。
エコを意識して生活をする
通勤や買い物などの移動手段を見直すことも、CO₂削減の有効な手段です。徒歩や自転車、公共交通機関の利用を心がけることで、自動車の使用を減らすことができます。
また、地元産の食材を選ぶ「地産地消」や、過剰包装を避けることなども、日常生活に取り入れやすい行動といえるでしょう。
環境情報に関心を持ち続ける
四日市市では、公式サイトや広報誌を通じて環境に関する情報を発信しています。こうした情報に日頃から目を通し、自分にできる取り組みを見つけていくことが大切です。
また、公害の歴史を学び直すことで、現在の豊かな環境が多くの犠牲と努力の上に築かれたものであることを再認識できます。こうした姿勢が、持続可能な未来への第一歩となるでしょう。
四日市は公害を乗り越えて住みやすい街に変化している!
四日市市は、かつて「四日市ぜんそく」に象徴される深刻な公害問題に直面し、多くの教訓と痛みを経て、現在では環境先進都市として再生を遂げました。公害防止協定の締結やモニタリング体制の整備、企業のクリーン化推進、市民参加型の環境保全活動など、多方面にわたる取り組みが実を結び、空気や水の質は大幅に改善されました。
公害を乗り越えられたのは、市民・企業・行政が一丸となって取り組んできたからこそ実現できたものであり、今後も継続的な努力が求められます。私たち一人ひとりが環境問題を自分ごととして捉え、日常の中でできる行動を積み重ねることが、四日市の環境を守り、より良い未来を築く上では欠かせません。
公害の歴史を風化させることなく、未来への教訓として次世代に伝えながら、持続可能な四日市市をともに目指していくことが今後ますます重要といえるでしょう。