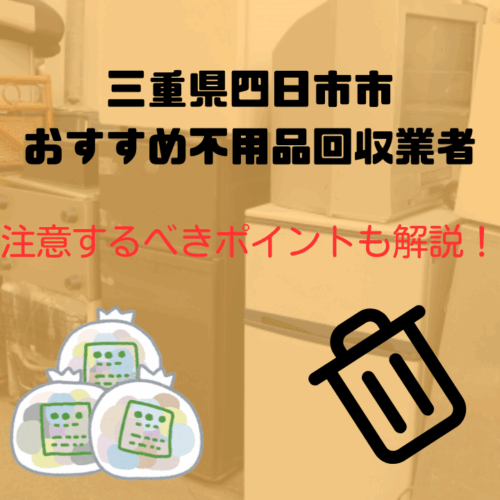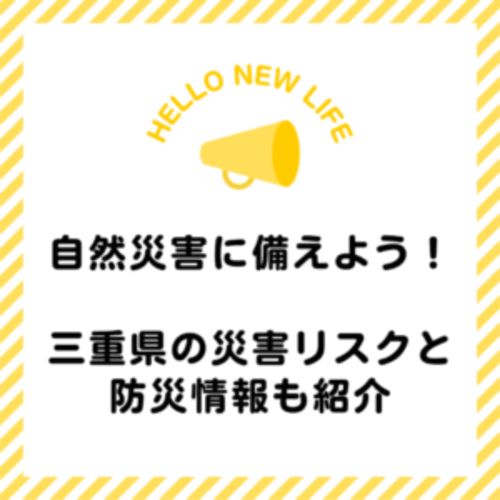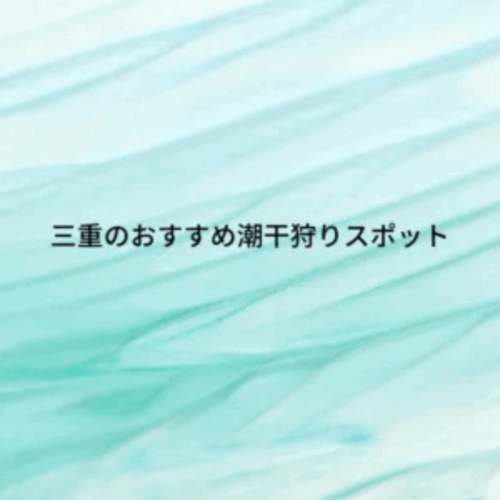「三重県に移住したいけれど、防災面が不安・・・」と感じている方は多いのではないでしょうか?
南海トラフ地震や水害などに、どのように備えて地域を選べばいいのか、具体的な方法が分かりにくいですよね。
私も実際に三重県への移住を考えたとき、「安全な場所はどこなのか」を必死に調べた経験があるので、その気持ちが痛いほど分かります。
この記事では、防災を意識した三重県での移住先選びや自治体の支援制度、日常生活でできる備えを詳しく紹介します。
三重県で比較的安全なおすすめ移住エリアもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
※本記事では災害リスクに触れますが、移住先を安心して選ぶための参考としてまとめています。あくまで移住を前向きに検討するための参考情報としてご覧ください。
三重県に移住するなら防災を意識すべき理由とは?

三重県は海・山・川に囲まれた自然豊かな土地です。一方で、地震・津波・台風・豪雨といった自然災害のリスクを抱えていることも事実です。
特に南海トラフ地震は将来発生が予測されており、沿岸部を中心に大きな被害が想定されています。
また、木曽三川流域では洪水や浸水の危険があり、毎年のように台風や集中豪雨に備える必要があります。
こうした状況から、三重県に移住する際には「住む場所の安全性」をしっかりと見極めることが必要不可欠です。
家族と安心して暮らすには、災害リスクを理解し、あらかじめ対策を考えておく必要があります。
ここでは、「なぜ移住を考えるときに防災を重視すべきなのか?」を、地震や津波、水害の観点から整理していきます。
南海トラフ地震と三重県の防災リスク
結論から言うと、三重県で移住を考える人は南海トラフ地震を避けて通れません。
なぜなら、三重県は東海・近畿の両方に位置し、地震や津波の被害想定地域に含まれているからです。
内閣府や気象庁の資料によると、南海トラフ巨大地震が起きた場合、三重県の沿岸部は津波の影響を大きく受ける可能性があります。
具体的には、尾鷲市や志摩市の沿岸では津波の高さが10mを超えるシミュレーションも発表されています。
こうした数字を見ると、移住先を選ぶ際に「どの地域が安全か」を調べることが必須だと分かります。
参考:三重県「地震被害想定調査結果(ハザード関係)の概要について」
三重県で想定される主な災害(地震・津波・水害)
三重県は海・山・川に囲まれた自然豊かな土地です。その反面、災害リスクとして代表的なのが「地震」「津波」「水害」です。
地震と津波は先ほど触れた通りですが、近年はゲリラ豪雨や台風による水害も増えており、四日市市や桑名市など木曽三川流域では、川の氾濫による浸水被害が心配されています。
実際、四日市市では今月2025年9月に記録的な大雨を記録し、近鉄四日市駅前の地下駐車場が水没したことは全国ニュースでも取り上げられていました。
また、南海トラフ巨大地震で津波被害が特に深刻になると想定される区域「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」は、以下の三重県の市町村が指定されています。
- 南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域
- 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、鈴鹿市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、川越町、明和町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町(全16市町)
一方で、三重県内の伊賀エリアは津波のリスクが低く、比較的安全な地域といえます。
つまり、災害リスクを総合的に考えて移住場所を選ぶことが、三重県ではとても大切なのです。
防災の視点から見る三重県の移住おすすめエリア

三重県の中でも、地域によって災害リスクは大きく異なります。
ここでは、津波や水害の影響を受けにくい内陸部や山間部、さらに生活の利便性と安全性を両立できる都市近郊エリアについて解説します。
三重県内陸エリア│津波リスクが低い
津波の心配を避けたいと考えるなら、三重県の内陸エリアは有力な選択肢になります。
特に津市や松阪市の市街地から少し山側に入った地域は、津波浸水想定区域に含まれない場所が多く、比較的安心できる土地といえます。
これらのエリアは伊勢自動車道や近鉄線を利用しやすく、名古屋や大阪方面へのアクセスも良好です。そのため、仕事や学校で大阪や名古屋に通う必要がある世帯でも、暮らしやすい環境が整っています。
さらに、子育て世帯にとっては、自然に囲まれた落ち着いた環境で子どもを育てられることも大きなメリットになります。
例えば津市では、移住者を対象とした空き家バンク制度や住宅改修補助金の制度を設けており、耐震性のある家を手に入れるサポートも行われています。
防災の観点から安全性を確保しつつ、支援制度を活用すれば経済的な負担も軽減できるでしょう。
つまり、三重県の内陸エリアは「津波リスクが低い」「都市部へのアクセスが良い」「住宅コストを抑えやすい」という3つの強みを兼ね備えた移住先の一つです。
三重県山間部エリア│水害に強い
伊賀市や名張市は山に囲まれ、津波の心配がほとんどありません。
もちろん、川沿いでは水害リスクを考える必要がありますが、市がハザードマップを公表しているため、水害が心配な方はハザードマップを確認のうえで、地域を選びましょう。
また、伊賀市は大阪や奈良へのアクセスが良く、通勤圏としても人気です。
さらに、古民家を活用した移住支援や起業支援にも力を入れているため、防災と暮らしやすさを両立できます。
バランスが取れたエリア│医療×交通×防災
三重県で移住を検討する際、多くの人が気にするのは「安全性」と同時に「生活の利便性」です。
いくら防災面で安心できても、病院が遠かったり、交通の便が悪かったりすると日常生活に不便を感じてしまいます。
そのため、防災と同時に医療や交通の条件も満たす都市近郊エリアは、子育て世帯やシニア層にとって特に魅力的です。
四日市市や鈴鹿市は、名古屋へのアクセスが良く、新幹線や高速道路を利用すれば関西方面へも移動しやすい立地です。
通勤・通学の利便性に加え、大規模病院や専門医療機関が揃っているため、万が一のときに安心できます。

出典:三重県立総合医療センター「病院のご案内」
また、市街地の平野部は水害リスクがある地域もありますが、近年は高台の新興住宅地が整備され、災害リスクを抑えた選択が増えてきています。
例えば四日市市では、地域ごとに指定避難所が整備され、災害時に迅速な避難ができるよう防災体制を強化しています。
さらに、鈴鹿市は大規模工業都市でありながら、市全域で「防災研修会」が定期的に行われており、住民同士の防災意識が高い点も安心材料です。
こうした都市近郊エリアを選ぶと、「防災」「医療」「交通」のバランスを取りながら暮らすことができます。
特に、将来的に子どもの進学や親の介護といったライフイベントが重なる世代にとっては、日常の安心と万一の備えを両立できる理想的な移住先と言えるでしょう。
参考:鈴鹿市「防災研修会」
三重県の自治体が進める防災・移住支援制度

三重県の各自治体は、防災と移住を結びつけた取り組みを進めています。
ここでは、防災拠点や避難体制、さらに移住者向けのセミナーや補助制度を紹介し、経済的にも安心して新生活を始める方法について詳しく紹介します。
防災拠点・避難体制│各市町村の特徴
三重県の多くの自治体では、防災拠点や避難所の整備が進められています。
例えば志摩市では、2つの津波避難タワーを建設し、沿岸住民の安全を守る取り組みを行っています。

出典:志摩市「11月2日 国府地区津波避難タワー完成式典」
津市や伊勢市では学校や公民館を避難所に指定し、地域住民がすぐに避難できるようになっています。
こうした取り組みを知ることで、移住希望者は「災害が起きたときも安心できる」と感じられます。
まずは、自分が移住を検討している地域の「避難場所はどこなのか?」「どんな場所なのか?」「どんな工夫がされているのか?」をチェックしてみましょう。
防災セミナー・相談窓口│三重県の移住者向け
自治体によっては、市民を対象にした防災セミナーを開催しています。
例えば熊野市では、地域の消防団や防災担当者が参加するイベントがあり、市民や移住者も気軽に学べます。
また、三重県庁や市町村の移住相談窓口では、住まい選びの際に防災情報も提供しています。
こうした仕組みをうまく活用し、移住計画を安心して進めていくのが良いでしょう。
補助金・支援金│安心の移住を実現するために
三重県では、移住者向けの補助金制度が整っており、住宅の耐震改修や空き家のリフォームに補助金を出す自治体もあります。
例えば、尾鷲市では空き家改修費用の一部を補助する制度があり、防災性を高めた住まいに安心して移ることができます。
このような移住者支援制度を利用すれば、経済的な負担を減らしながら安全性を確保できるので、移住後の安心感が大きくなります。
移住者支援制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:尾鷲市「尾鷲市空き家バンク利用促進助成金制度について」
三重県に移住して防災に備える暮らし方

防災を意識した移住は、地域選びだけでなく日常生活の工夫も大切です。
ここでは、家選びのポイントや家庭での備え、地域コミュニティとの関わり方を紹介し、安心できる暮らしを実現するための具体策を紹介します。
防災ポイント│家選びで必ずチェックしよう
住まいを探すときには、ハザードマップで災害リスクを確認することは必要不可欠です。
津波浸水予測区域や洪水想定区域を避けるだけでなく、地盤の強さも確認するとより安心です。地盤が弱いと地震で揺れが大きくなり、液状化の恐れもあります。
また、住宅の耐震性能や避難所までの距離もチェックしましょう。
「この家に住んだ時、自分がもし災害に遭ったら・・・」を具体的にイメージしながら家を探すのが、防災を意識する上で大切です。
移住後に整える│防災グッズと家庭の備え
移住した後も、防災意識を持ち続けることが大切です。
非常食や飲料水、モバイルバッテリー、簡易トイレなどの備蓄は最低3日分、できれば1週間分を準備すると安心です。
例えば、四日市市の防災ガイドブックでは、家庭で必要な備蓄リストが公開されています。
こうした情報を参考にしながら準備すれば、万が一のときも落ち着いて行動できます。
最大の防災?│地域コミュニティと繋がる大切さ
災害時には地域の助け合いがとても大切です。
自治会や町内会に参加し、防災訓練に顔を出すことで、いざというときに助け合える関係を築けます。
特に移住者は地域に馴染むまで不安がありますが、コミュニティ活動を通じて自然に交流が生まれます。
例えば、伊勢市では自主防災組織が活発で、移住者も参加しやすい環境があります。こうした繋がりは、防災面だけでなく日常生活の安心にも繋がるため、積極的に活用しましょう。
三重県の移住×防災でよくある質問Q&A

最後に、三重県への移住を検討する人が特に気にするであろう疑問を整理しました。
ここでは、南海トラフ地震の影響、住まい選びの判断基準、支援制度の利用方法など、よくある質問に答えていきます。
Q1. 南海トラフが心配だけど、三重県に移住して大丈夫?
A. 沿岸部は津波リスクが高いですが、内陸や高台は比較的安全です。
リスクが高いエリアでも、各自治体の防災対策も進んでいるので、「自分が移住を検討している市町村が、どんな災害対策を行っているのか?」を慎重に調べると、より安心でしょう。
Q2. 防災を重視するなら賃貸と購入どちらが安心?
A. 初めての移住なら賃貸を選び、ハザードマップや生活環境を確認するのが安心です。
地域に慣れたら、防災面を考えた上で住宅購入を検討しましょう。
Q3. 三重県で移住者が利用できる防災関連制度は?
A. 空き家改修補助金や耐震補強補助などがあります。
市町村によって制度が異なるので、事前に確認しましょう。
参考:美し国みえ「空き家改修補助金」/三重県「木造住宅の耐震関係支援制度」
まとめ|防災を意識した三重県移住で安心できる暮らしを実現
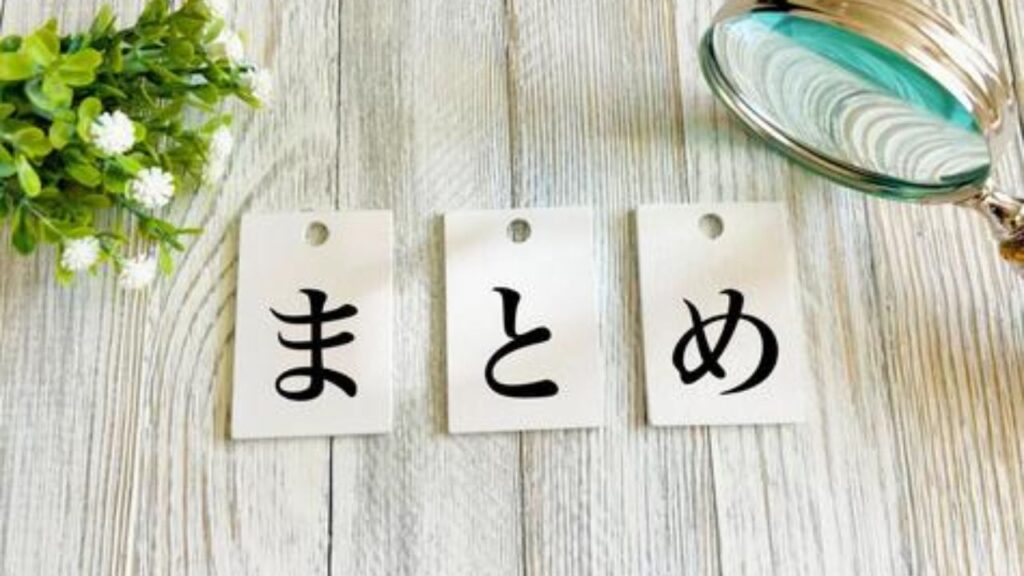
ここまで紹介したように、三重県に移住する際には、防災についても考えることが欠かせません。
安全な地域を選ぶことで家族の安心を守り、自治体の支援制度を利用すれば経済的な負担も軽くなります。
さらに、家庭での備えや地域の繋がりを築けば、日常生活も心強くなります。
防災を意識した三重県移住は、「安全な場所を選ぶ」「制度を活用する」「地域と繋がる」という3本柱が必要になってきます。
この3つを意識すれば、不安を減らして新しい生活を始めることができるのではないでしょうか?
最後までご覧いただき、ありがとうございました。